お金の情報格差
お金の情報格差ってあると思いますか?
そもそもお金の情報格差って?って思うかもしれませんね。私も30代後半までそんなこと考えたことも無いような金融知識なんてほぼ無いような人間です。しかし、ひょんなキッカケから保険会社に勤める機会があり短期間でしたが、「お金の情報格差」というものが存在しているなと知ることとなりました。
今回は身近な医療保険制度や保険についてです。病院にお世話になったら保険証必ず使うのでわかっていそうで
いざその制度について全部知っているかと聞かれてもネズコは分かりません💦
是非いっしょに詳しくなって、お金の不安をすこしづつでも解決していきませんか。
まずは公的医療保険制度について改めて知り、そこからいろいろ思ったことなどを書いていきますので、よかったらお付き合いください。

保険会社に勤めて気づいたこと

みなさんは保険にはいっていますか?
保険といっても沢山種類がありますが、勤め先で加入する社会保険や国民健康保険、民間の保険会社で生命保険や医療保険、火災保険、車の保険などありますね。
ネズコは主に生命保険などを扱う会社に居ました。保険会社で務めた経験も無いので右も左もわからない状態で入社しております💦
1年弱しか勤務しておりませんでしたが、そこで学んだことで考え方として良かったことなど紹介できたらとおもいます。
話は戻りますが、ネズコ自身も学びなおす気持ちで進めて参ります。
公的医療保険制度って改めて説明できる?

そういわれても、ネズコはちょっと自信ありません。
え?毎月支払っている健康保険のこと?会社で加入している社会保険でしょ。病院にかかったら保険が効いて3割負担になる。
みたいな。保険効かなかったら無茶苦茶に高額だから、入っとかなあかんやつ。
さ、改めて学ぼっと:lol:
これ実はちゃんと知っておくことで、民間の医療保険が必要か否かなどの考え方にも大切なことなんです!
日本国内では「国民皆保険制度」のもとで全国民は必ず何らかの公的医療保険に加入している
健康保険とは、会社員や公務員が加入することになる公的医療保険の名称です。
いわゆる勤務先の「社会保険」が健康保険、会社と折半して毎月のお給料から天引きという形で保険料を納めることになっています。
日本国内では「国民皆保険制度」のもとで全国民は必ず何らかの公的医療保険に加入していますが、そのおかげでケガをしたときや病気になってしまったときの医療費が1〜3割の自己負担で済むようになっています。
また、健康保険に加入していることで子供が生まれたときの「出産手当金」や、病気やケガなどの理由で働けない期間がある場合に支払われる「傷病手当金」などが受け取れる。
これらは自営業者やフリーランスが加入することになる「国民健康保険」では受けられない給付金なので、健康保険のほうが手厚い保障内容になるんだって。
じゃあ、国の保険と民間の保険の違いは?
大きな違いは、保障の適用範囲が広いか狭いかなのかもしれません。
公的保険では風邪のときでもケガをしたときでも、病院で健康保険証を提出すれば保障されますよね?
また出産時にも公的な保障が受けられますね。
一方の民間保険は、契約した内容により保障対象が違うというのが特徴で、主に入院費や手術費、死亡時など保障対象になることがおおいですよね。最近は働けない月のお給料分を毎月カバーするような考え方の保証などもありますね。

高額療養費制度を知ることが大事だよね
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初め
から終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給してもらえる制度。一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利みたい。
ちなみに、入院時の食費負担や差額ベッド代などは適用外になるよ。差額ベット代について私が調べたところによると、入院のときに部屋の指定(大部屋ではなく個室~4人部屋)をすると別でお金がかかるから、それは実費で払ってねっ!てことだとおもいます。
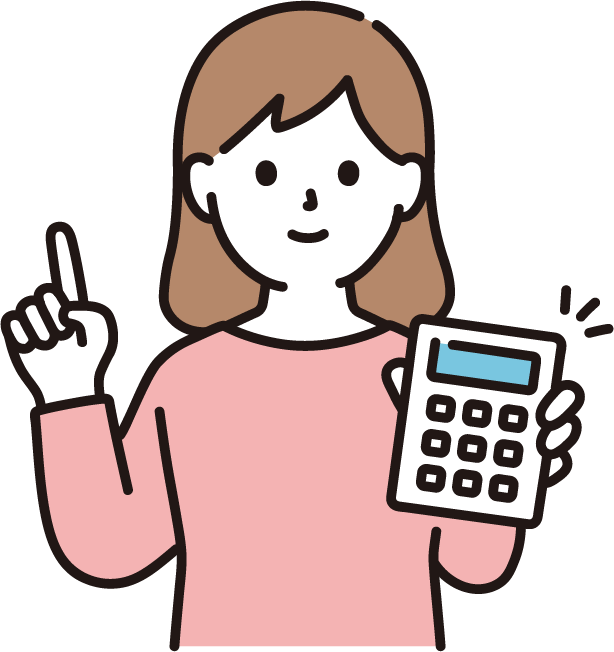
上限額は、年齢や所得によって違う
69歳以下の自己負担額は、5つの所得区分に分けられています。
一カ月の上限額(世帯ごと)はざっくりと下記ですが、詳しくは全国健康保険協会のサイトなどを確認してくださいね。
・住民税非課税者 35,400円
・年収約370万円 57,600円
・年収約370~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
・年収約770~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1%
・年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1%
見てもらうと計算式があるのと無いのがありますよね?
計算が必要ないのは☝上から二番目までは定額となっているそうです。
まずは、自分がどこに分類されるか確認ですよね。
これは世帯ごとの分類みたいなので、例えば旦那さんが働いていて、奥さんが主婦の場合は旦那さんの所得が奥さんにも適用されるということですね。
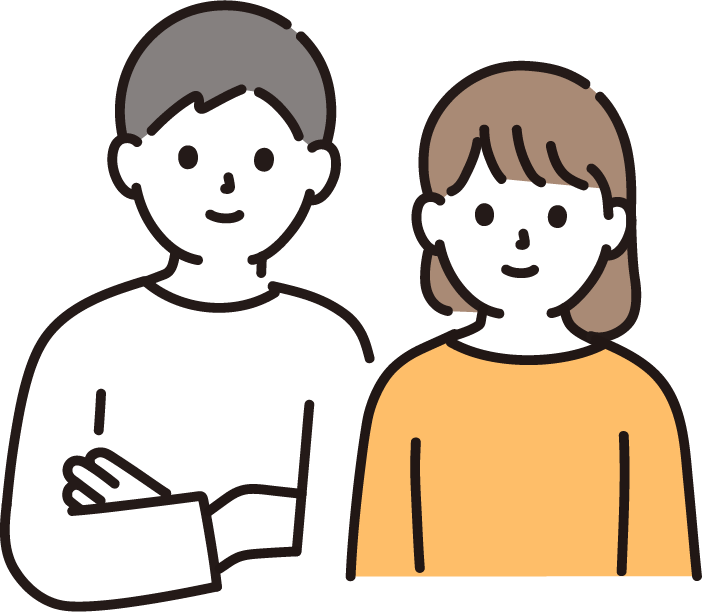
改めて高額療養費制度とは

日本では「国民皆保険制度」を導入しているため、全ての国民は何らかの「公的医療保険制度」に加入している!
そのため、公的医療保険制度に加入をしていると、医療費全額を支払うことはなく、医療費の一部を支払うことで治療を受けることができている!(~割負担ってのですね)
医療費に対する自己負担額は年齢、または所得によってその割合が異なる!
例えば小学校入学~69歳以下の年齢のひとは、かかった医療費の3割を自己負担し、残りは国の補助がでてる。
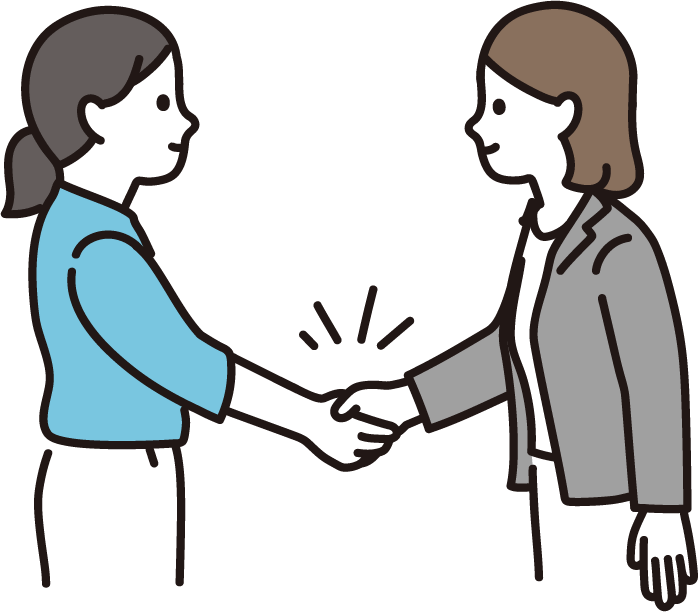

でも例えば長期的な入院や大きなケガの場合、自己負担3割の医療費が家計に対して負担となってしまう可能性もありますよね?
それが一番医療費で不安になるひとが多いのではないでしょうか?
保険とかのCMでもよく聞きますよね『万が一の入院のときの費用の~』みたいな。

そのため公的医療保険制度には、1カ月の自己負担額に、年齢や所得に応じて上限を定め、上限を超えた分の医療費を還付する制度があります。これが「高額療養費制度」です。
自己負担限度額の上限は年齢・所得によって違い、高額療養費制度で還付される金額は、1つの医療機関に限定されていなく
、同じ月の別の医療機関に支払った額も合計することができるため、1つの医療機関の支払いだけでは上限に満たない場合でも、合算することで高額療養費制度の支給対象とすることが可能。
注意が必要なのは、高額療養費制度は、本人希望による差額ベッド代や入院時の食費などには適用されません。あくまで医療費に対する制度。
これで大体、高額療養費制度について大事な部分はわかったような気がします!
民間の医療保険入っておいた方がいい?

これはわたしネズコの私見ですので参考までに!
わたしが保険会社で働いていたときの話です。
ベテランの保険外交員の先輩と医療保険について話していて、その先輩も、もちろん自社の医療保険に入っているものだと思っていたら加入していなかったんですよね。しかも、60代も近くなりそうな割と高齢の方だったんで、これから必要になってきそうな年齢だよなぁと('ω')?
ちなみにネズコの親や親戚など自分より年齢が上の人は大抵何かしらの医療保険に入ってる感じだったんで、よけいに「はて?」となりまして('ω')そして保険会社にいるのに自社の医療保険に入らんのですか?というような一般ピープルのそこにはネズコがいました。
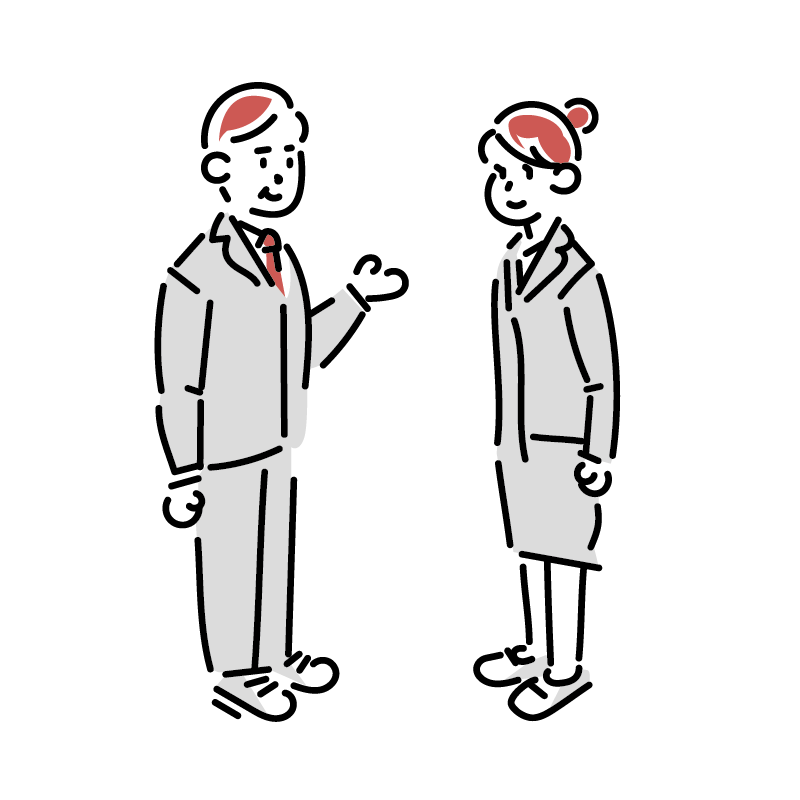
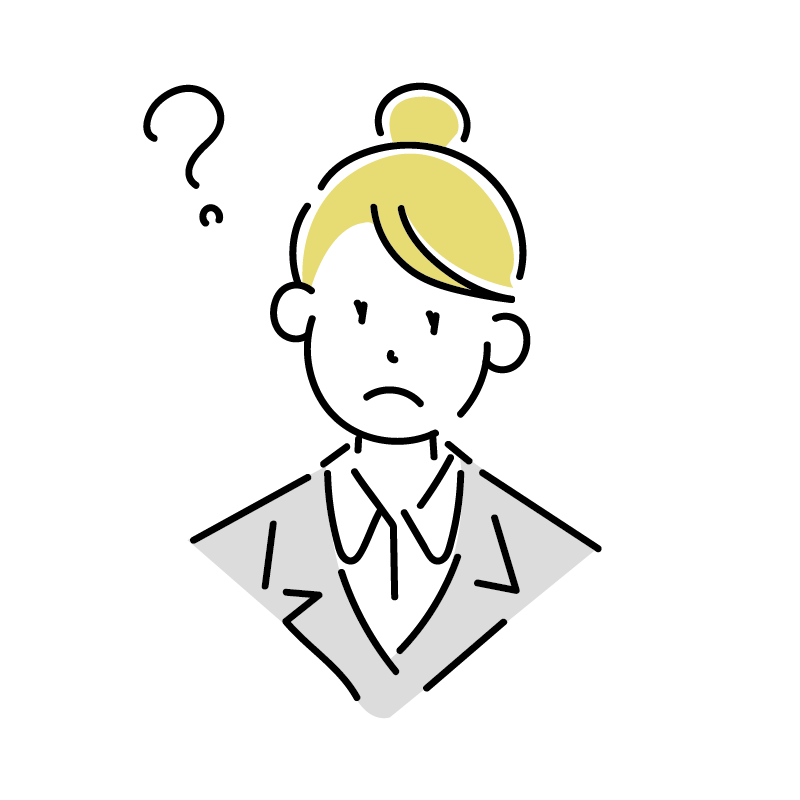
ちなみにその先輩の年収は800万~1000万くらいで暮らしにも余裕のある感じの方です。
その方が言っていたのは『医療保険は入る必要ないよ!』という、、これからいろいろ保険を人に紹介していく新人保険外交員の私にとっては衝撃の言葉だったのをいまでも覚えています。

その方が説明するには、やはり高額療養費制度がかなめになります。
民間の医療保険は多くは掛け捨てがおおいとおもいます。
ちなみに、掛け捨てとは、満期保険金がなく途中で解約しても解約払戻金がない(保険の)ことです。 掛け捨ての保険は、満期保険金などがある保険と比べて保険料が安く設定されているのが一般的です。
その方が言っていたのは、毎月長い期間掛け捨てで保険料を払うよりも、その代わりにお金を貯めておいた方がいいし高額療養費制度があるからその分だけは支払いできるように貯めてあるから入る必要が無いとのことでした。
なるほどぉ。でも貯めれない人は?とおもいますよね。ネズコも貯めれない方でしたので不安になります。
貯めれないなら、入っておいてもいいかもねっていう回答だったとおもいます。
いやぁ、今まで私自身がお客さんとして保険屋さんから話聞いてる時もそんな話聞いたことなかった!
だってまず初めに、月々いくらからなら支払いできるか?から話が進んでいたよなって。
それで入院したら一日いくらほしいかで設定していく感じだったかなぁ。
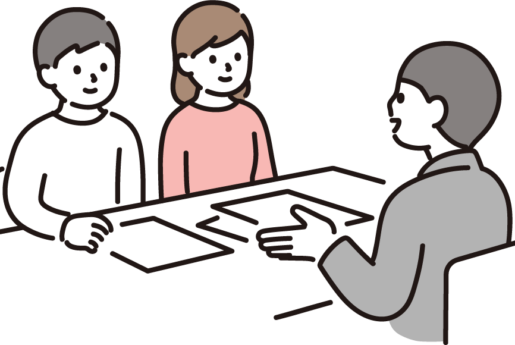


高額療養費制度のことはとくに触れられたことなかったなぁと。
私はその話を聞くまでは、民間の医療保険に加入することは社会人として当たり前みたいな、逆に入っていないのって大人として恥ずかしいことみたいなイメージでいました。それがまさかの、ベテランの保険営業マンは未加入っていう。
まずこれが、保険会社に勤めて驚いたことのひとつです。
ネズコ自身の育った環境では、親の知り合いのおばさん保険屋さんが私が小さい時から家や親戚のところによく来ていて、親も親戚もみんな加入していたので、入院したときなどの万が一の保険は入っておくのが社会人というか大人?みたいな考え方が自然と出来上がっていました。べつに悪いことではないとおもうのですが、それ以外の入らないという選択を尊敬できるベテラン保険営業マンの方がしていることが、わたしにとってはお金にも関連する新しい視点でした。
まずは、民間の医療保険から考えるのではなく、
日本では「国民皆保険制度」を導入しているから、全ての国民は「公的医療保険制度」に加入していて
公的医療保険制度に加入をしていると、医療費全額を支払うことはなく、医療費の一部を支払うことで治療を受けることができているし、公的医療保険制度には、1カ月の自己負担額に、年齢や所得に応じて上限を定め、上限を超えた分の医療費を還付する制度がある「高額療養費制度」があるから、これについてちゃんと理解してから民間保険加入の際には考えを反映させることが大事になるのではないかとおもうのです。
私ネズコにとってはわかっていそうで、わからない考え方でした。
私だけではなく、意外と民間の医療保険加入など考えるときに抜け落ちている視点だったきがしまする。
保険営業の方は親身な方もいるとおもいますし、親身だけど保険営業の方自身の毎月の営業成績の為に、お客さんにとっては本当は必要のない保険を勧められてしまう場合も大いにあると思うのです。
だから、保険屋さんだからと信じて任せきるのではなく、自分自身もお金に関すること(こんかいは医療費について)についての学びや情報をしっかり持ちたいものですよね。
ちなみに、誤解が無いようにいいますが民間の医療保険が必要ないといっているのではありません。
それは個人個人の考え方にもよってくるとおもいますし、少額ではありますが現在ネズコは入っています。
重要なのは、加入する本人が公的医療保険制度を理解したうえで、その他に補いたいことなどについて納得して加入していることかなとおもうのです。だから知らぬ間になんだか分からず、必要のない保険に長期間入ってしまっていて多額の金額を無駄にしたような気がする、、ってなんてことが無いように出来たら良いのではとネズコはおもうのです。
お金の情報格差はすぐ誰でも身近にある事実な気がするんですよね、だってこの間だってネズコはありましたよ(笑)
ちょっとしたことですが、損したなって( ;∀;)誰か教えてよおーって
それは、また今度の機会にはなしますが、そのくらい情報を知ってるか知らないかでお金事情って違ってくるんじゃないかと金融ど素人のネズコでもかんじるですわ!
まず、今回の記事はここまでとしてまた次回の記事で書いていきます。
今回は公的医療保険のとくに高額療養費制度について
学びながら記事をかきました!
まだまだ、学んでいくぞお~


